すこしまえに「#私を構成する9枚」が流行った。
「今時点の私にとってヴィヴィッド」というのとは違う。
ケツに抜かしてるもの、いや血肉化してるもの。血肉化してることを私自身意識できてるとは限らないもの。
それとの出会いによって私の世界が変わった、でも今の私にとっては当たり前の、音楽。
その意味で私を構成する、1枚目は、これだ。
①

「こんなに好き勝手やっていいんだ!」というショック。この「好き勝手」ということが、そのまま私にとっての「プログレ」の定義、と言い切って良い。
とんがったままごちゃついて、多様な可能性に開かれて、聴き手の耳を自由にし活性にする。この「ありよう」が、作品としての「完成度」に優先する。
完成度を測ることはものさしを前提とする。プログレは逆にものさしを疑うことだ。
そしてこの私のプログレ観を決定したのが、この『狂気』だった。
例えば、最近やけに好評の BAROCK PROJECT が、私には「約束づけられた問いの立て方への約束づけられた回答のし方」にしか聴こえなくて、全くワクワクしないのは、私のプログレ観がつまりそういうことだから。
②

「夢見がち」な少女を「覚醒」させた1枚。
音楽は音楽自律の「方法」に徹せねばならない。
音楽作品が「幻想的」「シュール」であっていけないわけではないが、私の、イメージありきでその表層をなぞり音楽に置き換える企て(描写音楽、標題楽の発想)は、悉く不毛に終わった。
このアルバムと出会って、作曲のスタンスが変わったし救われた。
このアルバムをシュールと評することも出来るかもだが、「シュールを作曲・表出してる」わけではなく、逆に「システム」を設えることに徹してるふうに見える。その中に放り込まれた音の素材が物理的即物的に振る舞うための。音の振舞いが「作曲・表出」のコンヴェンションを逸脱してるので結果としてシュール、ということはあり得る。
結果を予定しないこと=新たなシュールを拓くこと。
③

4曲中3曲が、帯に記載の Gong Kebyar Dharma Santi による演奏。
最後の1曲は別グループの演奏で、スリン・ガンブの編成。
ゴン・クビャールのほうは、派手な響きと超絶速いテンポで、「バリのガムラン」鑑賞欲をこれでもかと満たす。
でも私が魂持ってかれたのはガンブのほうで、響きが、イメージしてた「バリのガムラン」とまったく違ってた。幽玄というか、静謐で秘儀的。
けたたましいグンデルではなく、トライアングルみたいに高く澄んだ音色の金属打楽器(名前忘れた)や「鈴の木*1」でビートが刻まれ、主メロは数本のスリンのユニゾン。小節(こぶし)の多いメロディをユニゾンでやることで、モノフォニーでありつつ半ばヘテロフォニック。
音階も、分類すれば「ペログ音階」なんだろうけど、それで割り切れないこの世ならぬ調子。高音域で別の音階が接続されるように聴こえる。
このアルバムは日本公演時の録音。ガムランはいっぽうではコミュニティの「場」と結びついて「持ち運びできない」性質を持ってる。もういっぽうでは、そのあまりに高度な音楽を、音楽自体=芸能として切り離して、世界各地のコンサートホールをツアーして回るべき、また世界各地の演奏家によって取り上げられるべき、ユニヴァーサルな性格を持ってる。
私は例えば小泉文夫の現地録音にこそ「本物」を感じるけど、いっぽうで、音楽自体を聴くのに、アレンジの構造を完璧に捉えたこのアルバムの価値は高い。
④

⑤
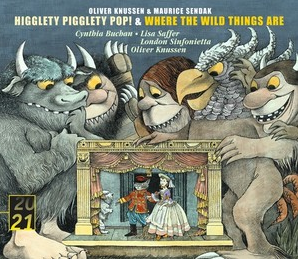
⑥

戦後のいわゆる現代音楽を、難解に戸惑ったり、能書に退屈したりしながら聴き進むのに、こういう、審美的な、響きとしてうっとりする音楽との出会いが励みになる。
Ohana は「オアナ」表記が一般的だろう*2。タイトルの 'Syllabaire pour Phèdre' の正しい訳(=作曲者の含意)は判らない。syllabaire(表節文字)は「音節を単位として表す表音文字」だから、そのいちばんよい例は、日本語の「仮名」。
*1:追記 2025年06月19日 ふと思い出して「グントオラグ」という楽器名だった気がした。こちらの「スマル・プグリンガン(Semar Peglingan)」についての御記事の「2.スマル・プグリンガンの楽器」のページ
https://www.ne.jp/asahi/pondok/gamelan/haru/sp_inst_index.html
に「グントオラッグ(Gentorag)」についての解説があった。「カジャール(Kajar)」と一緒の項目で挙げられてる。
「1976年までイギリス国籍であった」(Wikipedia「モーリス・オアナ」)とのことだから、このアルバムリリース当時は「オハナ」表記が妥当だったのだろうか?